マンション管理士&管理業務主任者はどうでしょう?(50代からの資格取得)
みなさんは、これら二つの資格をご存じでしょうか?
平成13年に施行されたマンション管理適正化法により創設された国家資格で、立場の違いはあれど、いずれもマンションを対象としており、試験内容も重なる部分が多いものです。
不動産系資格で有名な「宅地建物取引士(宅建士)」ですが、上記二つと合わせて「不動産三冠資格」と言われたりするみたいですね。
しかし、就職や転職は別として、分譲マンションにお住い(予定)の方へ、私が「宅建士」と「マンション管理士または管理業務主任者」のどちらをオススメするかというと、間違いなく後者になります。
宅地建物取引士の位置づけ
まず宅建士ですが、「宅地建物取引業法」に定められる資格で、法律の目的が第1条に定められています。
第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
要は、「取引」の公正を確保して、購入者等の利益の保護を図るわけですから、長い人生における場面としては、瞬間的・一時的な話になります。

瞬間的な話だと言っても、分譲であれば大金も動くわけで、もちろん慎重になる必要性はありますが、自分自身でも大事なことだと自覚するでしょうし、自然とチェックは厳しくなるものと思います。
マンション管理士と管理業務主任者の位置づけ
一方、マンション管理士と管理業務主任者は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に定められる資格で、こちらも法律の目的が第1条に定められています。
第一条 この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並びにマンション管理士の資格及びマンション管理業者の登録制度等について定めることにより、マンションの管理の適正化の推進を図るとともに、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
「管理業務主任者」はマンション管理業者の従業員なので、マンション管理士と並んで、同じ法律で定められていることになります。
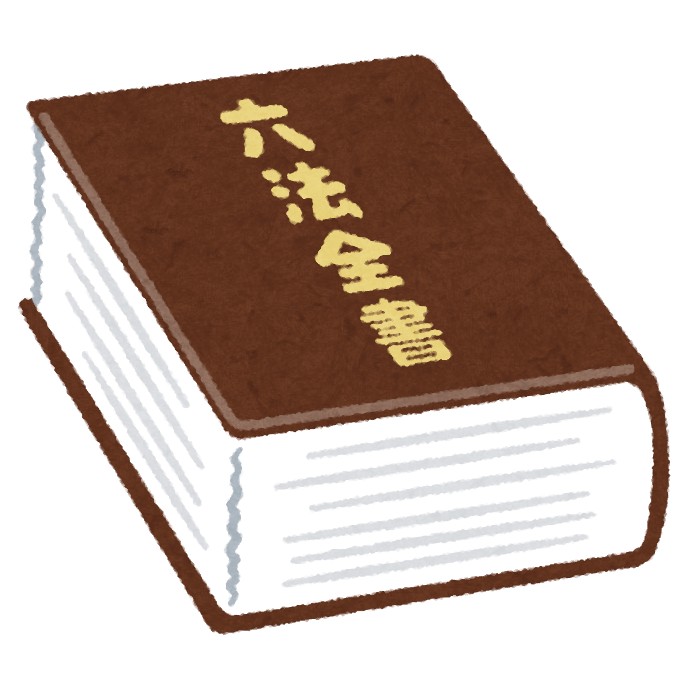
その目的は、「マンション管理の適正化」と「マンションにおける良好な居住環境の確保」ですから、ある程度の時間的継続性を前提とした話になるわけです。
なぜ宅建士よりオススメ?
就職や仕事とは関係なく、資格の難易度でもなく、分譲マンションにお住い(予定)の場合で、知識として役に立つ機会が多いかどうかという視点で、私は、この二つの資格を宅建士よりオススメします。
その理由ですが、宅建士よりもマンション管理士や管理業務主任者のほうが、分譲マンションに住んでいる場合に、その知識が有効になる機会が継続的にあるからです。

通常、分譲マンションの場合、共有者たる住人で管理組合が結成されますが、その役員は持ち回りであることが大半ではないでしょうか。
大規模マンションであれば、役員が回ってくる頻度は多くないにせよ、共有者として意思決定する機会は、総会などで少なくとも年に1度はあるはずです。
マンションは管理を買え?で書きましたが、同じ人が役員をしていること自体、非常にマズイわけで、何かのハズミで、みなさんが役員にイキナリ選任されることも、十分にあり得るわけです。
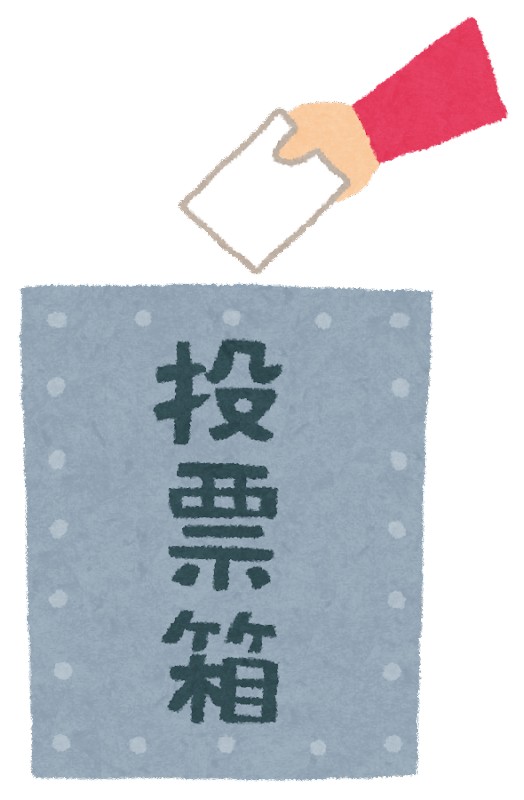
イザその時に、委託している管理業者に丸投げして、何事も起こらなければ良いのですが、金銭事故があったり、修繕での瑕疵があったりして、次の役員から責められる可能性もあり得るわけで…。
しかし、マンション管理士や管理業務主任者の知識があれば、別に資格まで取得していなくても、マンション管理業者に質問したり回答を求めることが容易になります。
一定の知識を背景とした具体的な質問と、的を得ないフワッとした質問では、管理業者の対応が変わってもおかしくないのです。
さらに管理業者としての立場から言えば、従業員のリソースは限られているわけで、緊張感のある管理組合にはエースの担当者を配置し、緩い管理組合にはそれなりの人を配置するかもしれません。

…あくまでも、可能性の話ですよ(笑)
宅建士の知識が必要な場面
宅建士は人気の資格ですが、知識の活用という面ではどうでしょう?
私の経験になりますが、今住んでいる中古戸建を購入する時に初めて、宅建業者と宅建士にお世話になりました。
その際、法的に宅建士が説明する必要ある重要事項説明をしていただきましたが、特段の問題はありませんでした。

人生最大の買い物ですから、重要事項説明のような最終局面ではなく、それ以前の段階で、徹底的に疑問を解消するようにしてはいましたが、宅建の知識がズバリ役立った記憶はありません。
そもそも、取引で本当に大事なことのために重要事項説明があり、そこにミスがあると宅建業者も処分を受ける可能性があるので、一定の実績ある宅建業者であれば、さほど心配ないものと思われるのです。
一方で、分譲マンションであれば、窓口体制の違いはあっても管理会社が入っていることが一般的で、理事会のサポートのほか、修理や騒音問題などで、お世話になる機会もあるのではないでしょうか?

つまり、分譲マンションにお住まい(予定)の方であれば、マンション管理士や管理業務主任者の知識のほうが、その後、継続的に役に立つ可能性が多いのです。
マンション管理士と管理業務主任者の違い
冒頭でマンション管理士と管理業務主任者の違いは「立場の違い」と説明しました。
立場としての大きな違いは、管理会社に雇われる立場か、そうでないかということになります。

マンション管理会社には、管理業務主任者を設置することが法律によって定められており、管理委託30件ごとに1人が必要になっています。
なので、管理会社が管理戸数を増やすほど、管理業務主任者が必要となるわけで、採用の場面なんかでは「有資格者歓迎!」となるわけですね。
この点は、宅地建物取引業者が営業する際に必要となる、宅建士とも共通してます。
一方で、マンション管理士は、他の士業と同様に独立開業系の資格であって、独占業務もありません。
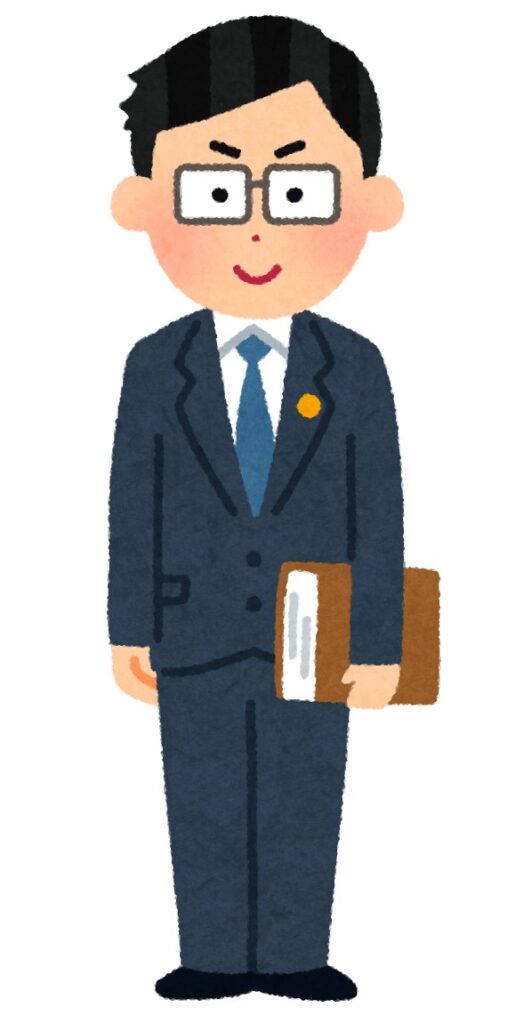
名称は独占ですが、管理組合からの相談に応じる形での業務が想定されているのです。
つまり、管理業務主任者は管理会社に所属して、管理業者の立場から説明やチェックを行う一方で、マンション管理士は管理組合側の立場から、資産保全や管理運営のアドバイスを行うことになります。
合格率の違い
直近5年間の各試験の合格率等は以下のとおりです。
| 管理業務主任者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 合格点 |
| 平成29年 | 16950 | 3679 | 21.7% | 36点 |
| 平成30年 | 16249 | 3531 | 21.7% | 33点 |
| 令和元年 | 15591 | 3617 | 23.2% | 34点 |
| 令和2年 | 15667 | 3473 | 22.2% | 37点 |
| 令和3年 | 16538 | 3203 | 19.4% | 35点 |
| マンション管理士 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 合格点 |
| 平成29年 | 13037 | 1168 | 9.0% | 36点 |
| 平成30年 | 12389 | 975 | 7.9% | 38点 |
| 令和元年 | 12021 | 991 | 8.2% | 37点 |
| 令和2年 | 12198 | 972 | 8.0% | 36点 |
| 令和3年 | 12520 | 1238 | 9.9% | 38点 |
合格率では倍近くの差があるほか、どちらも競争試験のため試験年度で多少の変動ありますが、合格点も平均では1~2点違います。
どちらがオススメ?
マンション住まいなら宅建士の知識よりも、関係性深いのがマンション管理士と管理業務主任者と言うのは分かったと。
では次に、どちらの資格がオススメなの?となるかと思います。
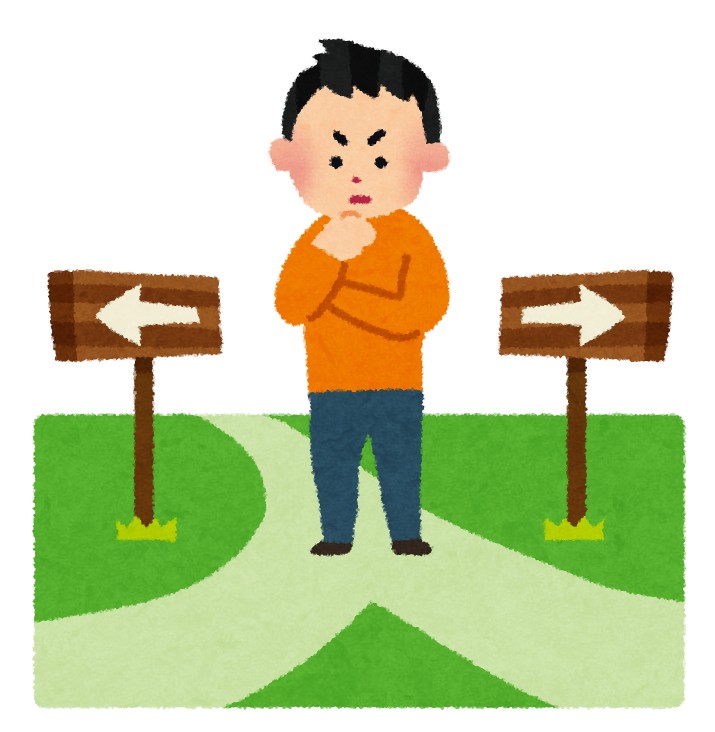
合格率で見ると、マンション管理士試験は管理業務主任者よりも低く、難易度の差がうかがえます。
結論としては、資格を取得するという目的であれば、試験範囲が8~9割に重なっているほか、試験時期も近いので、ダブル受験が非常に効率が良くてオススメです。
実際、私もダブル受験をして同時に合格しています。
私のような資格マニアではなく(笑)、役に立つほうだけ取りたいということであれば、管理業務主任者の取得をオススメします。
理由は以下の3つです。

①管理業務主任者試験の勉強範囲であっても、マンション管理全体の知識を得られること
②比較的、就職や転職に有利な資格であること(=マンション管理士の求人は少ない)
③マンション管理士より難易度は低いですが、合格するとマンション管理士試験で5問免除を受けられること
しかし、管理会社に対してビシビシとモノ申したい!という方は、難易度が高くても、マンション管理士のほうが多少でもニラミが効くかもしれません。
というのも管理会社では、管理業務主任者の資格には受験料や褒賞金を援助することあっても、マンション管理士は対象でないことがあり、意外とマンション管理士は持っていない従業員も多いので…(笑)
まずはじめに…
私が受験・合格したのは5年以上前になりますので、オススメのテキストや問題集については、今、自信を持ってオススメできるものはありません。
当時は、もちろん独学ですが、さすがに1か月の学習期間というようなものではなく、3~4か月はミッチリと勉強をしました。

既に宅建士は取得していましたので、民法などの基本的な考え方については既習だったとも言え、それがなければ半年は必要だったかもしれません。
半年の勉強、しかも独学となると、モチベーションの維持だけでも結構タイヘンです。
そのため、就職や転職等で絶対に取りたいという理由がない限り、興味を持てそうかくらいは、初めに確かめたほうが良いのではないかと思うわけです。
最近フラッと、図書館に行った時に見つけた本がこちらですが、1日もかからずに軽く読んでしまえる内容で、かつ、初めての「ツカミ」にはピッタリと感じましたのでご紹介します。
この本だけで、合格はバッチリ間違いなし!ということはサスガに言えません(笑)
しかし、試験勉強をするにあたって、その全体像が見えるというのは何より大事で、ボンヤリとした感じであっても、これから何を勉強しなければならないかを把握できるのは大きいです。
興味はあるけれども、半年も勉強できるかどうか分からない…ということであれば、一度、本書を読んでみると良いかもしません。

資格まで取る必要なければ、管理組合の理事会役員必読書としても良いくらいの内容だと感じました(笑)
建築・設備系が難しいかも
文系の方にとって敬遠したい勉強範囲の一つに、建築や設備系の知識があるかと思います。
しかし、この資格を取るべきポイントの一つは、マンションの修繕計画を理解することだと私は考えてまして、この分野こそ勉強する価値があると思っています。
というのも、住戸ごとの修繕積立金は多く見えないかもしれませんが、全体で見れば、マンションの維持管理のため、毎年、相当の金額が修繕に使われているハズです。
問題が大きくなってから慌てるよりも、前もって計画的にトラブルを予防したほうが、効果や費用の点でも優れているのは、人間の体に限ったことではなくマンションも同様です。
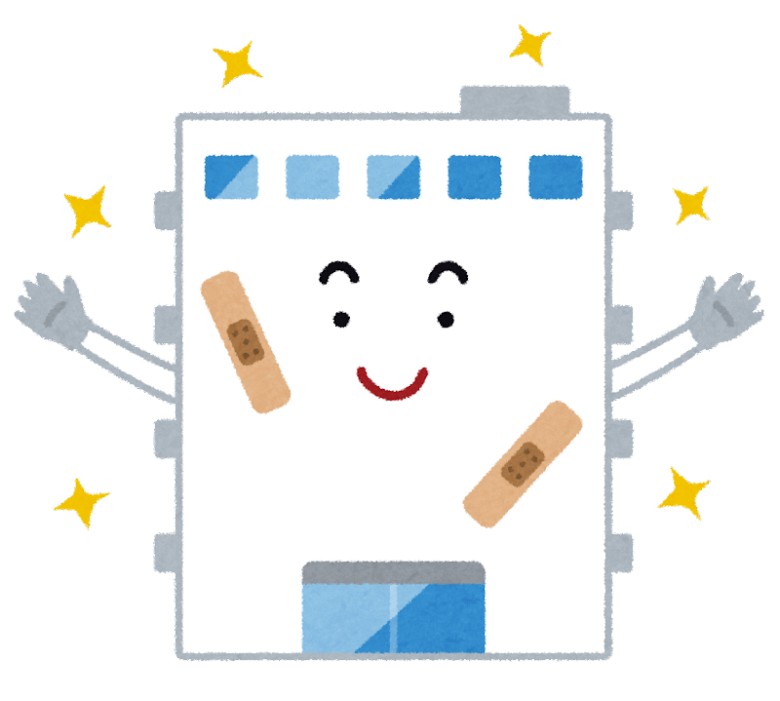
しかし、建築系の仕事をされている方であればともかく、そうでなければ、目に見える部分はともかく、隠蔽部分については知る由もないわけです。
修繕計画の理解のためには、マンション全体に係る建築、設備、給排水、電気などの知識が必要ですが、基本テキストで詳細に触れているものは少なく、理解不足になる可能性があります。
そのための補助教材として、以下のような設備の図解本が有効ですし、私も実際に利用していました。
なんでもそうなんでしょうが、知らないから不安になるだけで、いったん絵や図で理解できるとなんでもありません。
私もド文系なので分かるのですが、文系の意識があると、技術分野の知識はとかく敬遠しがちなのですが、現場の技術は理論より実践で、単純と感じる場合さえあるくらいです。
理論の裏付けあったほうが良いのは事実でしょうが、現場で作業される方が、必ずしも全員が理系ではないことからもお分かりいただけるかと思います。
管理業者と適切な関係を保って、大切なマンションの資産価値を維持するためにも、建築、設備系の知識を、この機会にしっかりと習得してください!
老後はマンションへ?
子育てに伴う騒音を気にしたこともあって、現時点で私は戸建住宅を選びましたが、老後になって、マンションに住み替える可能性が十分にあります。
車も手放す必要があるでしょうし、病院も近くに必要でしょうし、何かにつけて便利な駅近のマンションこそ、高齢者に最適なのではないかと思うのです。

とは言っても、コスパ重視な私ですので、新築プレミアムのない手頃な中古マンションを買って、予算の範囲でリノベーションするだろうと妄想しています。
もちろん、購入に際しては徹底的に管理会社に質問して、修繕履歴や共用部分の管理運営実態を調べ、管理会社の評価もセットに判断することになるだろうと思います。
何しろ、マンションは管理を買え?ですから!
ずっと同じ人が理事長をされていたり、ずっと同じ管理会社に委託している場合は、闇が深い可能性もありますし…。
晴れてマンション購入に至った場合は、率先して理事会の役員に手を挙げて、「おとぴんさんが役員やってくれて助かるわ~」とか、みなさんに都合よく使われるつもりです(笑)